木造2階建:構造計算不要なのだけど、、、【府中市の不動産屋さん】

目次
「木造戸建住宅」の構造計算
大きな震災が起こるたびに住宅の倒壊について報道されますが、日本の住宅で一番多い「木造戸建住宅」の構造計算について知っておきましょう!
といっても、結構難しい話なので、ふ~ン、そんなこともあるんだなぁくらいでよいかと思います(笑)
一般的な木造戸建て住宅(階数が2以下)は
「4号建築物」とか「4号建物」と言われており、建築確認申請時に構造計算の審査を簡略化することが認められています。
「4号建築物」とは

4号建築物とは、建築基準法第6条第4号で規定する建物のことで、具体的には以下の条件に当てはまる建築物です。
・木造の建築物
・階数2以下
・延べ面積500m2以下
・高さ13メートル以下
・軒の高さが9メートル以下
つまり、3階建てを除く木造戸建住宅のほとんどが該当します。
それでは「構造計算の審査を簡略化できる」について説明します。
構造計算書の審査の簡略化とは

建築基準法第20条第1項4号 木造2階建て住宅等の4号建築の「耐震性等の構造耐力」について
(イ)当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること(建築基準法施行令40~49条による仕様規定。)
(ロ)前三号に定める基準のいずれかに適合(=構造計算を行うこと)すること。(許容応力度計算などの構造計算を指します。)のいずれかに適合する事となっています。
(イ)の仕様規定における構造の簡易な検討方法として、以下の3つの方法があります。
1.壁量の確保(壁量計算)
2.壁量バランス(4分割法)
3.継手・仕口の選択・柱頭柱脚金物のチェック(N値計算法)
ここでは主に、地震力や風圧力に対抗するために必要な壁(耐力壁)の量が確保されているかどうかのチェック、耐力壁がバランスよく配置されているかどうかのチェック、柱の上下がしっかり緊結されているかのチェックを、それぞれ計算によって確認します。
つまり、木造2階建て住宅等の4号建築は、この(イ)の方法を採用すれば、建築基準法上は構造計算書がなくても確認申請が承認される事になります。
さらに木造2階建住宅等の4号建築は建築基準法第6条の3三号にて、建築士が設計をすれば壁量計算書や構造関係の図面を確認申請に添付しなくて良いとされています(いわゆる4号特例)。
つまり、耐震性などの構造耐力に関わる仕様規定を満たしているかの検討書や図面も、確認申請に提出を求められず、本当に法律に適合しているのかは、役所はノーチェックということになります。
※ただし、注意したいのは審査を簡略化できても「構造の安全性をチェックしなくても良い」ということではありません。
構造の安全性のチェックはどんな建物でも必要
2階建て以下の木造戸建て住宅でも構造の安全性を確認する必要はもちろんあります。
建築確認申請時の審査が省略されているだけで、守らなければならない計算や仕様のルールが決まっています。
工務店に構造について確認しておこう

上記のように一般的な在来木造、2階建て以下の建物では、確認申請時に複雑な構造計算は求められず、審査の簡略化(4号特例)が認められています。
しかし、それは構造の安全性のチェックをしなくて良いということではなく、
建築基準法で定められた計算方法と仕様規定を設計士が守って設計するだろうから「役所はチェックしない」という意味にすぎません。
これからご自宅を新築される場合は、確認申請で書類の提出こそ要求されませんが、これらの方法によって建物構造の安全性がチェックされているかどうかを、施工会社に質問していただくと良いです。
最近では、在来工法2階建てであっても、構造計算書等を出してくれる工務店などもあります。
構造計算書は費用が掛かる話しになりますが、構造計算に基づいて建築されていれば、地震などの災害時も一定の安心材料になることは間違いありません。
といっても、構造計算がなくともしっかり作られている物件もあったりしますので、ここが難しいところですが、将来売却の際には、建物が安全に建築されているという担保資料として役立つことでしょう。
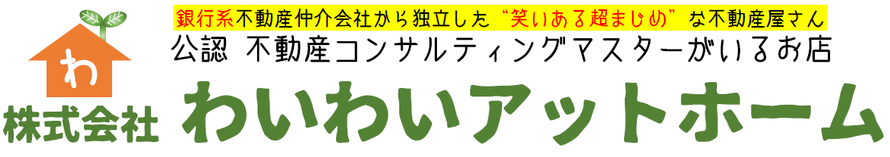

コメント