売却や購入を、まだ決めなくていなくても大丈夫です
状況整理だけでもOK。営業目的の連絡は行っていません。
※以下のような方が多く利用されています
・売却や購入で迷っている
・相続/共有で話が進まない
・他社で断られたケース
お急ぎの方は 042-319-8622
この時点で売却を決める必要はありません。ご安心ください。
状況整理だけでもOK。営業目的の連絡は行っていません。
※以下のような方が多く利用されています
・売却や購入で迷っている
・相続/共有で話が進まない
・他社で断られたケース
お急ぎの方は 042-319-8622
この時点で売却を決める必要はありません。ご安心ください。

1 共有不動産を賃貸することは、共有者全員の合意が必要な「処分行為」なのか。
2 それとも共有者の過半数で決めることができる「管理行為」なのか。
ーーー
昔々あるところに、相続によりビルの1室(事務所)を共有する3名がおりました。
兄弟は仲良く睦まじく、いつも楽しい兄弟でした。
いつも意見がそろう奇跡の兄弟と巷では評判でしたが、人生屈折70年、今回初めて意見が分かれました。
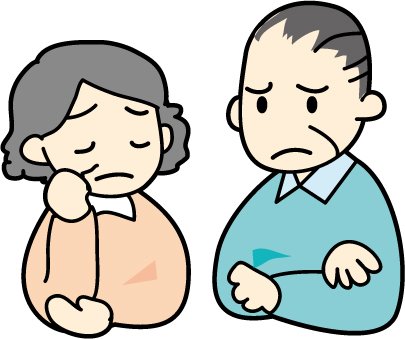
事務所を相続したときは賃借人がいたのですが、先日退去してしまい空室になりました。
兄弟のうち2名は「今後も事務所を賃貸に出して賃料収入で稼ごう!」といい、
兄弟のうち1名は「今回は貸すのはやめようよ!」と言いました。
2名は賃料収入が目的ですが、
1名は将来「自分が」その事務所を使いたいと心の中で思っていたのです。
共有の建物を賃貸借契約をする場合、共有者の持分の過半数の同意があれば賃貸できるのでしょうか?と言うのが今回の論点です。
共有不動産の賃貸は、相当の事情があれば持分の過半数で可能となる場合もありますが、原則は共有者全員の同意が必要です。(宅建の試験だと過半数の同意でOKになっています。)
不動産に限らず、共有物の現状を変える行為の内容によって、必要な共有者の同意割合が変わります。
共有物は、各共有者は持分に応じた使用ができる(民法第249条)事になっていますが、共有不動産(一戸建ての場合)を持分に応じて使用することは現実的に難しいのです。
部屋の大きさが違ったり、土地の位置が違ったり、条件が異なりますから、公平な使用ができない可能性が高いのです。今回のように事務所の一室であれば、賃貸にしたその家賃収入を単純に3等分に配分するというのは、最も合理的で簡単であるとも言えます。

(新築・増築・改築・土地の造成や、抵当権設定・売買などの法律的な処分行為)は
多額の費用がかかり、兄弟全員にかなりの影響を与えるため、全員の同意なく行えません。
普通に考えればわかります。(民法第251条)
(賃貸・賃料変更・賃貸借契約の解除・賃借権譲渡の承諾)は
持分の過半数によって管理が可能です。(民法第252条前段)
(修繕や不法占拠者に対して明け渡し請求する事など)は
各共有者が単独で行うことができます。(同法第252条但書)
物件の価値を維持させるための行為ですから、
兄弟姉妹3名は誰も損をしないし、結果として得をする行為です。
今回の兄弟姉妹3名のケースは、賃貸人として共有建物を賃貸借契約をする事は、契約期間が短期賃貸借契約(民法第602条)で、同法で定める一定の期間を超えない場合は、管理行為であるとの考え方もあるため、全員の同意なしに賃貸契約をしても良いという事になりそうです。
しかし、裁判例では、契約期間が短期間であっても、一度賃貸に出してしまえば、更新される可能性が高く、大家さんからの正当な事由なく賃貸借契約の解除はなかなかできるものではありません。
そうなると、共有者による使用や収益に及ぼす影響は無視できませんから
「賃貸借契約の締結も、原則として、共有者全員の合意なくしては有効に行い得ない」として、
共有物の賃貸借契約の締結は、変更行為として共有者全員の同意が必要であるとされることもあるのです。
共有の商業ビル(一室の事務所)の賃貸借契約において、他の兄弟が自己利用する必要がないときに、商業ビルの賃貸による収益が各兄弟に還元される場合「持分権の過半数によって決することが不相当とはいえない事情がある場合には、長期間の賃貸借契約の締結も管理行為(持分の過半数の同意でOK)に当たる」としていることもあります。
つまり、3名の事情等により解釈が異なるという事にもなるため、一方的に法律がこうなっているからいいんだ!と言うような事でもないようです。
宅建試験であれば、管理行為(持分の過半数の同意でOK)ですが、実際には杓子定規にはいかないようです。
法律ってほんと難しいですね(笑)
参考になりましたか?(笑)


状況整理だけでもOK。営業目的の連絡は行っていません。
※以下のような方が多く利用されています
・売却や購入で迷っている
・相続/共有で話が進まない
・他社で断られたケース
お急ぎの方は 042-319-8622
この時点で売却を決める必要はありません。ご安心ください。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント